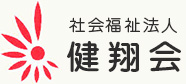自由と節度
2025.11.18
かつては近所へ出るだけでも上着を着用し、姿勢を正していた時代がありました。身だしなみは、自分を律するための小さな“けじめ”でもあり、同時に地域社会への礼儀でもありました。その行為の中には、「節度をもって暮らす」という生活のリズムが確かに息づいていました。
いま、私たちの暮らしは大きく様変わりしています。普段着のまま外へ出ることが当たり前となり、生活の延長線がそのまま公共空間へ流れ込むようになりました。気軽さは便利さをもたらしますが、一方で“生活感があまりに露骨に外へあふれ出る”光景も増えています。人前であっても平気でスマホに没頭し、道端での飲食や迷惑行為が話題になることもあるなど、節度の輪郭が薄れてきたように見えます。
その背景には、「自分が良ければそれでいい」という空気の広がりがあります。自由や個性の尊重は歓迎すべき流れですが、行き過ぎれば社会全体のけじめが曖昧になります。本来、公共の場とは多くの人が共有する“中間領域”であり、最低限の節度があるからこそ心地よく成り立つ空間です。しかし、個の自由が強調されすぎると、その中間領域の規律が崩れ、互いが気を配る文化が後退してしまいます。
服装の変化は、単なるファッションの問題ではありません。それは社会観の変化そのものであり、「どこまでが自分の領域で、どこからが他者との共有空間なのか」という感覚を表しています。普段着で外出する自由そのものは否定されるべきではありませんが、そこに節度や気遣いが伴うとき、社会はより心地よいものになります。
自由と節度。そのバランスを失わずに暮らせるかどうか――現代の私たちが立っているのは、ちょうどその境界線の上なのかもしれません。