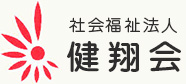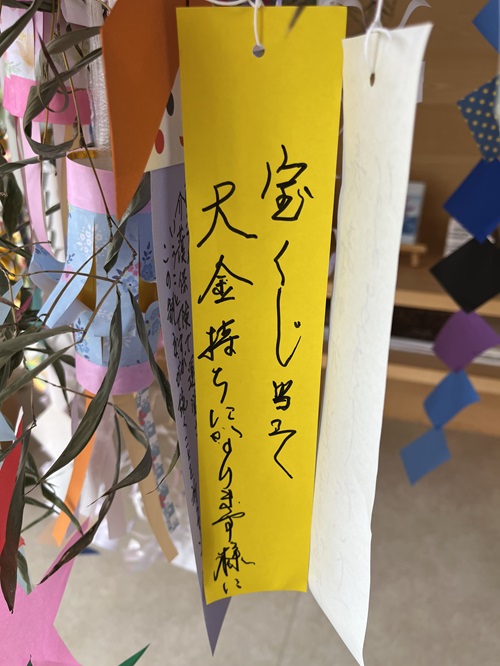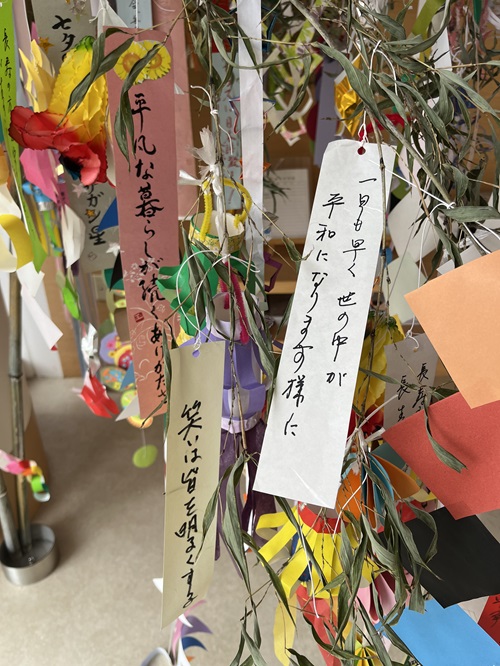理事長コラム
門司誠一の思いをつづります。
-
2025.07.02
本日10時30分から令和7年度鳥栖市放課後児童クラブ連絡会が当法人会議室で開催され、山下雄平参議院議員、鳥栖市から生涯学習課長もお越しいただき、意見交換が行われました。山下雄平参議院議員からもご挨拶もあり、併せて木下健蔵会長(社会福祉法人公栄理事長)から山下雄平参議院議員に要望書が提出されました。


-
2025.04.01
令和7年度辞令交付式が本法人会議室で厳粛に執り行い、今年は新人職員1名と中途採用3名に辞令を手渡しました。社会福祉法人の一員として、新たなスタートを迎えられた皆さんを心から歓迎いたします。
本法人は、職員が安心して働ける環境を整え、支援していくことをお約束します。これから皆さんと共に、良い福祉を築き、皆さんの今後の活躍に期待し、心からエールを送ります。

-
2025.02.27

入居者様の手作りお雛様 雛人形は、五節句のうちのひとつ「上巳の節句(じょうしのせっく)」と、日本の平安時代に流行した「ひいな遊び」の2つが合わさって生まれた風習です。
古代中国では旧暦3月の最初の巳の日(みのひ)に、水辺で身体を清め災厄を祓うという風習があり、その習わしが日本にも伝わりました。
日本では3月3日の上巳の節句の日に、紙や草木などで人の形をした「人形(ひとがた)」と呼ばれるものを作り、その人形に病気や災いを移し川に流す「巳の日の祓(みのひのはらい)」という儀式が行われていました。
これが「流し雛」と呼ばれる風習になり、雛人形の由来になったと言われています。
また日本では、平安時代に貴族の女の子の間で「ひいな遊び」と呼ばれるお人形遊びが流行しました。
「ひいな」とはもともと小さくて可愛らしいものを表す言葉で、このひいな遊びには紙や布で作られた人形を使って、現代のおままごとのような遊びをしていたようです。この平安時代の女の子の間の遊びで使われていた「ひいな」と、上巳の節句に用いられた「人形(ひとがた)」が長い年月を経て結びついたものが雛人形の起源と言われています。
その後江戸時代初期に京都御所で雛祭りが催されたことをきっかけに幕府の大奥で雛祭りを行うようになったことでその風習が地方へ広まり、雛人形は女の子のあこがれの対象となりました。
そこから現代のように上巳の節句に雛人形を飾る華やかな雛祭りに変化していったと言われています。