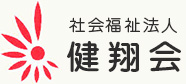――社会福祉法人の経営現場から見た課題と希望―
高市政権が発足し、日本社会は新たな転換期を迎えている。人口減少と超高齢化が進み、地域の力が弱まりつつあるいま、政治がどのように「持続可能な福祉」を構築していくのかは、社会全体の命運を左右する課題である。社会福祉法人の経営に携わる者として、私はこの政権に、理念だけでなく現場の経営実態に即した政策展開を強く期待している。
福祉経営の現場では、まず「人材確保」と「処遇改善」が最大のテーマである。人材は法人の資本そのものだ。採用が難しいだけでなく、離職防止や育成にも長期的な視点が求められる。いま必要なのは、単なる賃上げ政策ではなく、職員が将来設計を描けるようなキャリア構築支援と、地域間・法人間の格差を是正する仕組みだ。福祉人材の確保・育成を国家戦略の一部として位置づけてほしい。
また、社会福祉法人の経営は「公的責任」と「経営合理性」の両立という難題を常に抱えている。限られた介護報酬の中で質を維持しながら経営を成り立たせるためには、効率化と創意工夫が不可欠だ。しかし、現在の制度は報酬体系・補助金制度・監査基準が複雑で、現場は事務負担に追われている。高市政権には、現場を信頼した制度の簡素化、そして成果を「書類」ではなく「利用者の生活の質」で評価する柔軟な仕組みを求めたい。
財政面では、社会保障費の増大が避けて通れない中で、「持続可能性」と「公平性」の両立が問われている。高市氏が掲げる「全世代型社会保障」の理念は評価できるが、その実現には、国・自治体・事業者・国民それぞれが適切に負担を分かち合う構造が必要だ。たとえば、社会福祉法人が地域の公益活動(見守り、防災支援など)を担う際、財源が伴わなければ継続は難しい。補助金や交付金を単発的な事業ではなく、中長期的な地域インフラ整備の投資と位置づけてほしい。
加えて、社会福祉法人が今後の地域経営に果たす役割も大きい。かつては「施設を運営する法人」という認識が強かったが、これからは地域の課題解決に主体的に関わる「地域経営体」へと進化する必要がある。たとえば、医療・介護・子育て・障がい福祉を横断的に連携させ、地域の暮らしを丸ごと支えるような取り組み。そこに政策的な支援と柔軟な規制緩和があれば、法人の持つ人材・ノウハウ・信頼を生かした新しい地域づくりが進むはずだ。
経営の視点で言えば、デジタル化と人の力の調和も鍵を握る。DX(デジタルトランスフォーメーション)はもはや避けて通れないが、導入コストや運用支援なしに現場が対応できるわけではない。ICT化は人件費削減のためでなく、「人が人に向き合う時間を生み出すための投資」として位置づけるべきだ。高市政権が得意とするテクノロジー分野で、福祉DXの基盤整備を進めてほしい。
また、災害・感染症・エネルギー危機といったリスク対策も、経営の重要課題になっている。施設は地域の避難拠点であり、命を守るインフラでもある。国土強靭化を掲げるなら、その中に「福祉・医療・防災の連携強化」を明確に位置づけてほしい。非常用電源や備蓄設備への支援、緊急時の物資・人材供給体制の整備など、具体的な施策を期待する。
社会福祉法人は、民間企業とも行政機関とも異なる立場にある。公共性と自立性を両立させながら、地域社会に密着した経営を続けていくためには、政治の理解と後押しが欠かせない。高市政権には、現場の声を丁寧にすくい上げ、「制度を作る側」と「支える側」が対話できる関係を築いてほしい。
福祉の経営は、数字だけでは測れない「人の幸福」を扱う経営である。だからこそ、効率よりも持続性、成長よりも信頼を大切にしたい。国の政策がその価値観と歩調を合わせるとき、福祉は単なる支出ではなく、社会の未来への「投資」として機能する。
地域を支える現場の努力と、国が描く政策の方向がしっかり噛み合えば、日本の福祉はまだ進化できる。高市政権には、「現場の実感に根ざした政治」をぜひ実現してほしい。それが、真に豊かで温かい国づくりの第一歩になると信じている。